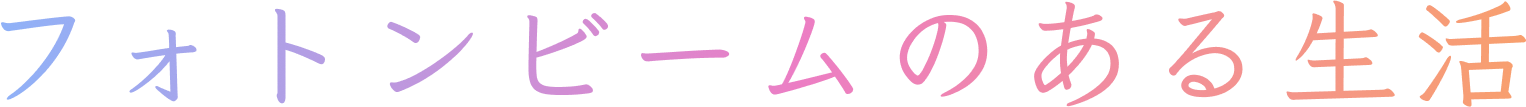フォトンビーム関連用語集
フォトンビームに関する用語集です。わかりにくい用語もできるだけかみ砕いた説明を心掛けています。いずれもフォトンビームの効果効能を謳うものではありません。
英数字
- DNAの個性差
-
従来の栄養学やサプリメントが効く人・効かない人がいる原因。フォトンケアは物質ではなくエネルギーとしてアプローチするため、この個性差の影響を受けにくい。
- NK細胞(ナチュラルキラー細胞, Natural Killer Cell
-
生まれつき体内に備わっている自然免疫の一種で、感染細胞やがん細胞を自律的に攻撃・排除する免疫細胞のことです。NK細胞は「リンパ球」に分類され、T細胞やB細胞と同じ仲間ですが、抗原の認識(学習)を必要とせずに働ける点が特徴です。 主にウイルス感染細胞や腫瘍細胞を見つけて、直接攻撃(細胞障害作用)を行います。
- RIFE REMEDY(ライフ レメディ)
-
キャンプラが販売していた、ライフ周波数を水に転写させる周波数発生器。フォトンビームの前身にあたる商品。
- pH(potential of Hydrogen)
-
溶液の酸性・アルカリ性の度合いを示す指数。水中の水素イオン濃度([H+])の常用対数(逆数)で定義される。
- pH 7:中性(純水)
- pH < 7:酸性(H+が多い)
- pH > 7:アルカリ性(OH−が多い)
フォトンビームや電解などの外部刺激により、酸化還元反応や電子供与体の変化を通じてpHがわずかに変動することがある。pHは生体活動(水素結合・酵素反応・ミトコンドリア代謝)にも密接に関係する。
- SOD/カタラーゼ(抗酸化酵素)
-
体内で自然に存在する抗酸化防御システムの主要酵素群。
- SOD(Superoxide Dismutase):スーパーオキシドラジカル(O2−)を過酸化水素(H2O2)に変換する酵素で、銅・亜鉛・マンガンなどの金属イオンを含む。
- カタラーゼ:過酸化水素(H2O2)を水に分解し、酸化ダメージを抑える。
これらの酵素が第一段階の防御ラインとなり、活性酸素から細胞を守る。
- ATP合成(ATP synthesis)
-
生体エネルギーの通貨であるATP(アデノシン三リン酸)をADP(アデノシン二リン酸)とリン酸(Pi)から合成する反応。
この反応は主にミトコンドリアのATP合成酵素(ATP synthase)によって行われ、電子伝達系(ETC)で生じる膜電位(Δψm)がエネルギー源となる。
膜電位差を利用し、プロトン(H+)が流れ戻る力(化学浸透圧)によってATPが生成される。
- NADH/NAD⁺(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)
-
生体内で電子をやり取りする主要な酸化還元補酵素。
- NAD+:電子を受け取る酸化型。
- NADH:電子を渡す還元型。
このペアが細胞内での酸化還元反応を仲介し、エネルギー代謝の要となる。電子伝達系ではNADHが電子を渡すことでATP合成の起点となり、フォトンビーム研究ではNADH/NAD+比の変化が還元状態の指標とされる。
- ROS(活性酸素種:Reactive Oxygen Species)
-
酸素分子が部分的に還元されてできる反応性の高い酸化性分子群。電子伝達系の副産物として生じ、細胞内損傷の主要因となる。
- スーパーオキシド(O2−)
- 過酸化水素(H2O2)
- ヒドロキシラジカル(•OH)
適度な量ではシグナル伝達に使われるが、過剰になると酸化ストレスを引き起こす。生体はSOD・カタラーゼ・グルタチオンなどの抗酸化システムで制御している。
あ行
- アポトーシス(apoptosis)
-
細胞が自らのプログラムに従って秩序立って死ぬ現象(プログラム細胞死)。病的な壊死とは異なり、炎症を起こさずに細胞が整理される生理的プロセス。
誘導要因:
- DNA損傷や酸化ストレス
- ミトコンドリア膜電位(Δψm)の喪失
- カスパーゼ群の活性化
ATPの減少やROSの過剰はアポトーシスの引き金となるが、フォトンビーム照射などでミトコンドリア機能が回復すると、抑制・細胞保護につながるケースも報告されている。
- エネルギー保存の法則(Energy Hozon no Hōsoku)
-
エネルギーは形を変えても全体として一定に保たれる原理。波動共鳴においても、複数の周波数のうち共振しやすい周波数のみが効率的にエネルギーを伝達する。
- 遠隔共鳴(Enkaku Kyōmei)
-
毛髪や爪は持ち主と離れていても周波数で共鳴するという現象。RIFE LIFEおよびRIFE REMEDYを用いた実験で立証された(メーカーは公式には否定)。
- 炎症性サイトカイン(inflammatory cytokines)
-
免疫細胞どうしの「連絡係」として働き、感染・外傷・ストレス・がんなどの刺激に応答して、免疫システムを活性化します。 しかし、過剰に分泌されると慢性炎症や自己免疫疾患、老化促進、組織破壊を招くこともあります。
代表的な炎症性サイトカイン:
- IL-1β(インターロイキン1β)
- IL-6(インターロイキン6)
- TNF-α(腫瘍壊死因子α)
- オートスキャン機能/マニュアル検査
-
波動共鳴機器の検査方法の分類。IMEDISは深く原因究明を行うためマニュアル検査を行う。
- オリジナルランプ
-
キャンプラが開発中のフォトンビームの最も重要な部品。
か行
- キャンプラ株式会社
-
フォトンビームの開発・製造販売元。スーパーエンジニアと発明家社長の二人で経営されている。
- 記憶の錯覚
-
脳が記憶を再生ではなく再構築する際に、想像的要素やスキーマが混入し、誤った記憶を信じ込む現象。
- 共鳴/共振
-
振動体固有の振動数に等しい外部振動の刺激を受けると振動が増大する現象が共鳴。その増幅が極限的に大きくなる現象が共振。調和した状態は共鳴した状態と同義。
- 極性(Polarity)
-
相反するもの。N極とS極、男性と女性のように、極性があることで調和が生まれる。
- 極性(Polarity)/極性異常(Kyokusei Ijō)
-
物質や生体のエネルギー場における正負のバランス。波動デバイスが劣化すると極性異常を呈することが、ドイツの量子共鳴装置「レヨコンプPS10」を用いた実験で確認された。外部要因(電磁波など)が極性異常を引き起こす可能性がある。
- 極性異常(Polarity Anomaly)
-
生体や物質のエネルギー場の正負のバランスが崩れた状態。電磁波などの外部要因で引き起こされ、波動グッズの劣化の主要因とされる。
- 木肌色(Kihada Iro)
-
調和の色として確認された色。日本人の一般的な肌の色に近く、自然なベージュトーンは心理的に安心感や落ち着きを誘う。
- クラスター(cluster)
-
複数の分子がゆるく結合してできた集合体(分子集団)。水では水分子同士が水素結合でつながってクラスターを形成する。
この構造は温度・圧力・電場・光照射などによって変化し、水の性質(味・溶解性・伝導度・ORPなど)に影響する。
小さいクラスターは水分子の動きが自由で反応性が高く、大きいクラスターは安定だが反応が鈍い。
- グルタチオン(GSH:Glutathione)
-
体内で最も重要な低分子抗酸化物質。グルタミン酸・システイン・グリシンからなるトリペプチドで、細胞内では還元型(GSH)と酸化型(GSSG)の形で存在する。
主な機能:
- 活性酸素や過酸化物の中和。
- タンパク質のチオール基(-SH)の保護。
- 解毒(グルタチオン抱合)。
- ビタミンCやEの再生補助。
GSHが酸化されるとGSSGになるが、グルタチオンレダクターゼによって再び還元型に戻される再生サイクルを持つ。
抗酸化システムの流れ:
- 酸化ストレス(フリーラジカル発生)。
- SODがスーパーオキシドをH2O2に変換。
- カタラーゼがH2O2を水に分解。
- GSHが残留過酸化物を還元・中和。
- 抗酸化状態を維持し、細胞の電子バランスを保つ。
- ケルビン温度(K)
-
絶対温度。水が最も密度が高くなる4℃(277K)は宇宙進化と共鳴する調和温度であるという仮説がある。
- 光子発生装置
-
フォトンビームの別称。電気信号がエネルギーになることを発見した装置。
- 抗酸化(antioxidation)
-
酸化によって生じる細胞損傷や老化を防ぐ働き。酸化は物質が電子を失うことであり、体内では活性酸素(ROS)が主因となる。抗酸化は電子を与えて安定化させる還元反応を行う仕組み。
抗酸化の仕組み:
- 酸化ストレスを受けた分子に電子を補い、フリーラジカルの連鎖反応を止める。
- 抗酸化酵素(SOD、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなど)が中心的に働く。
- 外部由来の抗酸化物質(ビタミンC、E、ポリフェノール、水素分子など)も補助的に機能する。
- 還元(reduction)
-
電子を受け取る反応。酸化(電子を失う)と対を成し、酸化還元反応の片側を構成する。
生体内では酸化された物質に電子を戻して安定化させる反応であり、ミトコンドリアのエネルギー生成や抗酸化反応で起こる。還元環境が維持されることで、DNA・タンパク質・脂質の酸化損傷が防がれる。
- 原子
-
物質を構成する最小単位のひとつで、化学的性質を保ったまま分割できない最小単位。
中心に原子核を持ち、その周りを電子が取り囲んでいる。電子の配置(電子殻構造)によって化学反応性や結合の仕方が決まる。
原子は電気的には中性(陽子数=電子数)で、光・熱・電場などの外部エネルギーによって励起やイオン化が起こる。
元素は同種の原子の集合であり、複数の原子が結びつくと分子になる。
- 原子核
-
原子の中心部分で、陽子(正の電荷)と中性子(電荷なし)からなる。
原子全体の質量の大部分を占め、陽子の数(=原子番号)が化学元素を決定する。
核反応(核分裂・核融合)によって巨大なエネルギーが放出される。フォトンビームや放射線の領域では、核へのエネルギー転移は非常に高エネルギー領域で扱われる。
元素は同種の原子の集合であり、複数の原子が結びつくと分子になる。
- 元素
-
同じ種類の原子(=同じ陽子数の原子)だけで構成された物質。周期表で分類され、水素・酸素・炭素など118種類(2025年時点)が知られている。
化学反応によって他の元素に変化することはない(核反応を除く)。フォトンビームの吸収・反射・透過は元素の種類によって異なり、波長選択性の基礎となる。
元素は同種の原子の集合であり、原子は原子核と電子で構成され、複数の原子が結びつくと分子になる。
一時的に体調や感覚に変化が現れる現象のこと。
体が新しい環境や刺激に適応する過程で、眠気・だるさ・発汗・一時的な症状の増減などが起こる場合があります。
一般的には「身体が回復へ向かう途中での調整反応」として説明されることがありますが、その感じ方や現れ方は個人差があり、必ずしも誰にでも起こるものではありません。
フォトンビーム利用時に体感の変化を感じた場合も、それが医学的な「効果」や「副作用」を意味するものではなく、体調変化の一例として受け止め、必要に応じて休息・医師相談を行うことが推奨されます。
さ行
- 酸化還元装置
-
フォトンビームの前身にあたる、最初に作った商品の一つ。
- 酸化還元(REDOX)
-
物質が電子を失う(酸化)、または電子を得る(還元)という化学変化。「酸化」と「還元」は常にペアで起こり、電子の受け渡しによって物質の性質やエネルギー状態が変化する。
例:
- 水素分子(H2)が電子を失ってH+になる → 酸化。
- 酸素分子(O2)が電子を受け取ってH2Oになる → 還元。
この過程は電池反応・光合成・呼吸・フォトン照射による電子移動など、エネルギー変換の中心的メカニズムである。
- 酸化還元電位(ORP:Oxidation-Reduction Potential)
-
溶液中の酸化・還元のバランス(電子のやりとりのしやすさ)を数値化した指標。単位はミリボルト(mV)。プラスが高いほど酸化的(電子を奪う力が強い)、マイナスが高いほど還元的(電子を与える力が強い)。
例:
- 酸化的:塩素水、オゾン水、漂白剤(+600mV前後)。
- 還元的:水素水、電解還元水(-300〜-800mV)。
フォトンビームなどの光照射が電子移動を促す場合、ORPの変化が酸化ストレス軽減や抗酸化作用の指標として測定される。
- 酸化ストレス(oxidative stress)
-
活性酸素種(ROS)やフリーラジカルが過剰に生成され、抗酸化防御力を超える状態。細胞成分(DNA、タンパク質、脂質など)が酸化され、機能障害・老化・疾患の原因となる。
主な原因にはミトコンドリアの電子伝達異常、紫外線・放射線・化学物質、慢性炎症・感染症などがある。フォトン照射や水素供与による電子移動は、酸化還元バランスを回復させ、酸化ストレスを軽減する方向に働くと報告されている。
- 細胞代謝(cellular metabolism)
-
細胞がエネルギーを獲得し、物質を合成・分解する一連の化学反応の総称。栄養素からエネルギー(ATP)を生み出す「異化」と、構造物質を作る「同化」の2系統に分けられる。
主な代謝経路:
- 解糖系(細胞質):グルコースを分解してピルビン酸とATPを生成。
- TCA回路(ミトコンドリア):ピルビン酸を酸化し、NADHを産生。
- 電子伝達系(ETC):NADHから電子を伝え、ATPを大量合成。
光や電子エネルギーが細胞に吸収されると、ミトコンドリア機能や代謝速度が変化し、ATP合成・抗酸化機能・修復能力に影響を及ぼす。
細胞内電子・代謝・ストレス応答の流れ:
- 栄養が取り込まれ細胞代謝(ATP合成)が進む。
- 電子伝達系が働きROSが発生する。
- 酸化ストレスが過剰になると炎症性サイトカインが放出される。
- Ca2+流入が増加しミトコンドリア膜電位が低下する。
- アポトーシス誘導または防御反応につながる。
- 細胞内カルシウム(intracellular Ca²⁺)
-
細胞の内外で濃度差(約1万倍)を保ちながら、シグナル伝達の中心的な役割を担うイオン。わずかなCa2+濃度変化が、代謝・分泌・筋収縮・遺伝子発現などを制御する。
小胞体やミトコンドリアがカルシウムを貯蔵・放出し、ミトコンドリアへのCa2+流入はATP合成を刺激するが、過剰流入はアポトーシスを誘発する。光刺激・酸化ストレス・電位変化などでカルシウム動態が変化する。
- 自己治癒力
-
人間の身体が持つ、薬に頼らず自分自身で健康を回復させる力。ホメオパシーやホリスティック医療で重視される。
- 自然欠乏症リスク
-
現代社会の生活環境がDNAにとって最適ではないという概念。
- 自由電子(free electron)
-
物質の中で特定の原子に束縛されず、自由に移動できる電子。金属や半導体の電気伝導の主役であり、エネルギーの移動や放出に関与する。
光照射などにより自由電子が励起されると、光電効果や電子伝達が発生し、生体では電子伝達系や抗酸化反応で自由電子の流れが生命活動を支えている。
- ジオパシック・ストレス
-
地磁気や地下水流など、環境から生じる微弱なストレス要因。
- シンクロニシティ(Synchronicity)
-
ユングが提唱した、因果律では説明できない意味のある偶然の一致。
- スピン
-
電子が動力源なしに持つ量子力学的角運動量。生命の「生」は回転(スピン)の存在として現れる。
- 周波数(Frequency)
-
振動数(Hz)で表され、音や電磁波の波動が1秒間に繰り返す振動。音楽、医療、通信、精神活動に広範な影響を及ぼす。
- 振動数(Shindōsū)
-
音や電磁波などの波動が1秒間に繰り返す振動の数で、単位はヘルツ(Hz)で表される。周波数は音楽、医療、通信、環境、精神活動にまで広範な影響を及ぼす。
- 水素結合(hydrogen bond)
-
水素原子が電気的に強く引き寄せる原子(酸素・窒素・フッ素など)の間で作る弱い結合。共有結合ほど強くないが、分子同士を秩序立ててつなぐ重要な相互作用。
水の場合、水分子(H2O)は酸素が電子を引き寄せるため分極し、「O-H…O」の形で隣の水分子と水素結合を形成する。この結合があるために、水は沸点が高く、氷は膨張して浮く。
フォトンビーム照射などで水素結合ネットワークが変化すると、水のクラスター構造・伝導度・ORP・粘性などが変わることがある。
- 水分子のクラスター構造最適化
-
水の調和作用の作用機序。量子化学的には電子軌道のエネルギー準位調整によるものと解釈できる。
た行
- ド・ブロイ波(de Broglie wave)
-
あらゆる物質には波動(=周波数)成分があることを示す理論。全ての粒子は周波数に変換可能であり、周波数としての性質を本質的に持っているとされる。
- 魂
-
肉体が滅びても不滅である存在。波動的な話にふさわしい概念。
- 中庸(Chūyō)
-
極端な極性(プラス/マイナス、善/悪)の中間、バランスの取れた状態。
- 調和(Harmony)
-
異なる要素やシステムが相互作用を通じて共振状態を形成する現象。愛よりも上の次元とされることがある。
- 電子
-
細胞内のミトコンドリアがエネルギーを作るために使用するもの。電子量が増えない限り、エネルギーは作れない。フォトンビームはダイレクトに電子を増やせるとされる。
- 電子ニュートリノ
-
フォトンビームが発信する粒子の名称の一つ。光子(フォトン)と同義で使われる。
- 電子不足
-
ストレス状態にある方が陥っている状態。フォトンケアはこの電子不足に有効とされる。
- 電位差(potential difference)
-
2点間の電気的な位置エネルギーの差を表す量。単位はボルト(V)。電子が移動する駆動力として働く。
電子は高い電位から低い電位へ移動し、エネルギーを放出または吸収する。電池の正極と負極の電位差によって電流が流れ、生体膜(ミトコンドリア膜など)でも電位差がエネルギー変換の源となる。
- 伝導度(electrical conductivity)
-
物質や溶液中で電気(電子やイオン)がどれだけ流れやすいかを示す指標。単位はシーメンス毎メートル(S/m)またはmS/cm。
例:
- 純水は伝導度が極めて低く、ほぼ絶縁体。
- 塩を溶かすとイオンが生じ、伝導度が上昇。
- 金属は電子伝導、溶液はイオン伝導で電気を運ぶ。
フォトンビーム実験などでは、照射によって水中の電荷バランスや伝導度が変化し、電子状態変化を間接的に観測できる。
- 電子伝達系(ETC:Electron Transport Chain)
-
ミトコンドリア内膜に存在し、電子を段階的に受け渡しながらエネルギーを取り出すシステム。NADHやFADH2から電子を受け取り、最終的に酸素(O2)に渡して水(H2O)を作る。
電子の移動によってプロトン(H+)が膜間へ汲み出され、膜電位(Δψm)を形成。この電位差を利用してATPが合成される。
主な構成要素:
- 複合体I(NADH脱水素酵素)
- 複合体II(コハク酸脱水素酵素)
- 複合体III(シトクロムbc1複合体)
- 複合体IV(シトクロムcオキシダーゼ)
- ATP合成酵素(Complex V)
な行
- ノイズ
-
意識や疑念がフォトンビームの動きを阻害する要因とされる。
は行
- バイオフォトン(Bio-photon)
-
生体が発する極めて微弱な光。細胞間の情報伝達に関与する可能性が指摘されており、がん細胞や老化細胞では放射パターンが無秩序(非コヒーレント)になる。
- バイオレゾナンス(Bio-resonance)
-
生体が発する微弱電磁波の周波数に着目し、共鳴(レゾナンス)の乱れを測定・調整して自己治癒力の回復を促す波動療法。ドイツを中心に医療・補完療法分野で使われ、IMEDISやベガテストと同じく共鳴原理を応用する。
フォトンビームなどの光エネルギーケアと併用すると、ノイズや極性異常で崩れた周波数パターンを整え、細胞の電子バランスやエネルギー循環を補正するサポート手段として期待されている。
- ヒューマンテレインシステム(Human Terrain System)
-
社会科学を兵器として利用するという概念。我々一人ひとりがデータ化された「地形」として扱われる。
- フォトンケア
-
フォトンビームを使ったケア方法。物質のアプローチでは限界のある方々への新しい救済の道とされる。
- フォトンビーム(Photon Beam)
-
小川陽吉氏が開発した光療法デバイスであり、光子発生装置。物質ではなくエネルギーレベルで細胞にアプローチする。
- フォトンビームエキスパート
-
フォトンビームの正しい使用方法を研究・教育するための育成コース。
- フリーラジカル(free radical)
-
不対電子(1個だけの孤立電子)を持つ非常に反応性の高い分子または原子。電子のペアが崩れた状態のため、他の分子から電子を奪って安定化しようとする。
代表的な生体フリーラジカル:
- スーパーオキシド(O2−)
- ヒドロキシラジカル(•OH)
- 一重項酸素(1O2)
呼吸や紫外線、放射線、炎症などで生成され、過剰に発生すると脂質過酸化やDNA損傷を引き起こすため、抗酸化システムによって除去される。
- ベガテスト(Vega Test)
-
1970年代にドイツで開発されたテスト。IMEDISの基礎となった周波数共鳴の原理。
- 波動粒子二重性(Hadō Ryūshi Nijūsei)
-
量子力学の概念で、電子や光子(光の粒子)は、あるときは粒子として、あるときは波(周波数)として振る舞うこと。
- 倍音(Baion)
-
ある音(基音)が鳴ったときに同時に発生する、基音の整数倍の周波数を持つ音のことです。 たとえば、弦楽器や声などで「ド(C)」を鳴らしたとき、実際には「ド」だけでなく、その2倍・3倍・4倍…といった周波数の音が同時に鳴っています。 これらが重なり合うことで、音色(ねいろ)が生まれます。
- 非接触・無痛・紫外線ゼロ
-
フォトンビームの使用上の安全性に関する特徴。激しいケアができない状態の者にも負担がかからない。
- 分子
-
2個以上の原子が化学結合(共有結合・イオン結合など)によって結びついた構造体。水(H2O)、酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)などが典型例。
分子は化学反応や光エネルギー吸収の基本単位として働き、光(フォトン)を吸収する際には分子内の電子遷移や振動・回転モードが関与する。
- 光の真空管
-
フォトンビームを指す表現の一つ。
ま行
- マクスウェル方程式
-
電磁気学の基本方程式。真空中の電磁波は横波のみとされる。
- 慢性不調
-
現代医療やサプリメントではカバーしきれない状態。フォトンビームはエネルギーのアプローチから対応できるとされる。
- 膜電位(Δψm:mitochondrial membrane potential)
-
ミトコンドリア内膜を隔てた内外の電位差(通常は内側がマイナス)。電子伝達系によるプロトン(H+)の移動によって形成され、ATP合成の直接的な駆動力となる。
膜電位は物質輸送(Ca2+や代謝物)を制御し、低下はミトコンドリア機能障害や細胞死の兆候となる。フォトン照射や電子供与によってΔψmが回復・安定化するケースが報告されており、生命活動のエネルギー効率と電子バランスの中心指標となる。
- ミトコンドリア
-
私たちのすべての細胞の中に存在する「エネルギーを生み出す小器官」です。 別名「細胞の発電所」とも呼ばれ、生命活動のほとんどに必要なエネルギーを供給しています。
主な働き
エネルギー(ATP)の合成
食事から得た糖や脂肪酸を分解して得られた電子を利用し、ATP(アデノシン三リン酸)という化学エネルギーを作り出します。
この過程を「細胞呼吸」または「酸化的リン酸化」と呼びます。
代謝の中心
クエン酸回路(TCA回路)を通して、糖・脂質・アミノ酸の代謝を統合します。
活性酸素(ROS)の産生
エネルギー生成の副産物として活性酸素種(ROS)が発生。
適度なら免疫反応に寄与しますが、過剰になると細胞障害や老化を引き起こします。
アポトーシス(細胞死)の制御
細胞が損傷した際に「自ら死ぬ」信号を発する役割も担っています。⚡ エネルギー産生の流れ(概要)
糖質・脂質が分解される → ピルビン酸・脂肪酸になる
TCA回路(マトリックス内)で電子を取り出す
電子伝達系(内膜上)で電子が運ばれ、水素イオン(H⁺)が膜の外へ押し出される
膜電位(Δψm)が生じる
ATP合成酵素(ATP synthase)がこの勾配を利用してATPを作る
→ まさに生体内の「発電システム」です。 - ミトコンドリア活性
-
フォトンビームによって細胞内のミトコンドリアが活性化される。シャーレ上での実験では40億倍活性させた。
- 未病(Mibyō)
-
西洋医学では捉えにくい、肉体に現れる前の「気」のレベルでの病態。波動測定は未病の段階での把握が可能とされる。
- Musubi Ultimate(むすび アルティメイト)
-
Musubiのさらに上位のケース。相性が良い物が限られる。
や行
- 溶存水素(H2, Dissolved Hydrogen)
-
水中に溶け込んでいる水素分子(H2)。濃度はppm(mg/L)で表される。水素は分子が小さく拡散しやすいため、時間とともに抜けやすい。
特徴:
- 強い還元性を持ち、電子供与体として働く(抗酸化作用の研究対象)。
- 溶存水素濃度が高いほど、ORP(酸化還元電位)はマイナス方向に低下する。
- 光・熱・攪拌・通電などにより濃度が変動しやすい。
水分子(H2O)と関連する要素:
- 水素結合がクラスター構造を形成する。
- pHがH+濃度で水の化学反応性を表す。
- 溶存水素(H2)は還元性(電子供与体)。
- 溶存酸素(DO)は酸化性(電子受容体)。
これらのバランスがORP(酸化還元電位)を決定し、水中の電子状態を左右する。
- 溶存酸素(DO:Dissolved Oxygen)
-
水中に溶け込んでいる酸素分子(O2)。生物の呼吸や水質評価の重要な指標で、単位はmg/L。
特徴:
- 大気中から水面を通じて溶け込む。
- 温度が低いほど溶けやすく、高温で減少する。
- 光合成(増加)や呼吸・酸化反応(減少)で変化する。
ORPや水質の酸化状態と密接に関係し、フォトン照射や電解では溶存酸素が電子受容体として反応し、活性酸素種の生成の起点になることもある。
ら行
- ライムのセリフ
-
映画『第三の男』のセリフ。「平和なスイスでは鳩時計しか生まれなかった」という、創造性と暴力の関連性を示唆する言葉。
- 量子医学(Ryōshi Igaku)/波動医学(Hadō Igaku)
-
物質レベルではなくエネルギーレベルで細胞や身体にアプローチする視点。フォトンビームの作用機序の基礎概念。
- 量子もつれ(Quantum Entanglement)
-
離れた場所の粒子が瞬時に情報を共有する現象。植物の光合成やDNAにも確認されており、自然界の量子知性を示唆する。