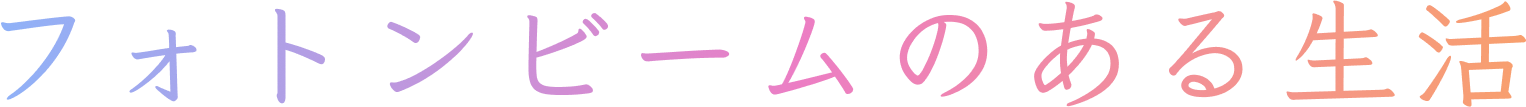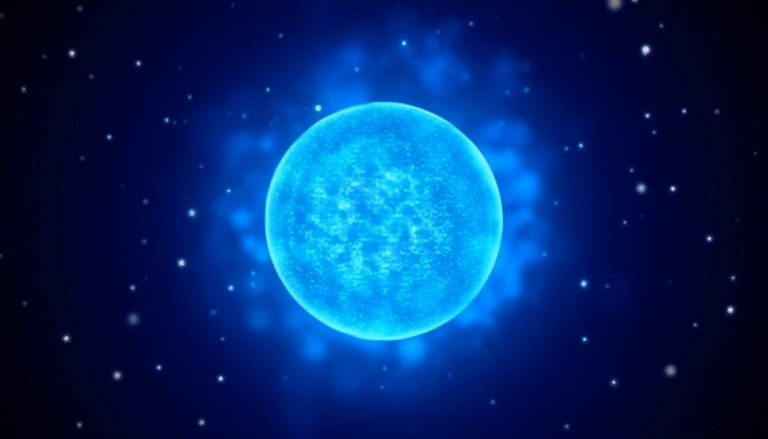✅この記事はこんな方におすすめ
- 電子の基礎知識を知りたい人
- フォトンビームがミトコンドリアにもたらす影響を知りたい人
この記事のポイント
- 電子は負(マイナス)の電気を持つ小さな粒で、電流や化学反応の主役
- イオンは電子を受け取ったり渡したりして生まれる、電気を帯びた原子や分子
- 化学反応は電子のキャッチボール。食塩や水ができる仕組みを例で解説
- ミトコンドリアは電子とイオンの流れを利用する細胞内の「発電所」
1.電子とは?
電子は、原子の外側を回るとても小さな粒で、負(マイナス)の電気を持っています。太陽の周りを惑星が回るように、電子は原子核の周りを常に動いています。電子の電気の大きさは約1.60×10^-19クーロンで、この値が電気の最小単位となっています。
原子の外側を回るとても小さな電子のイメージ
電子と電気の流れ
電気とは、電子が一方向に流れる現象です。ホースを流れる水に例えると、電圧は水圧、電子は水の粒のようなものです。電池や発電所から生まれた電子が導線を通って移動するとき、光や熱などのエネルギーを運びます。
電子が動くときに電気が発生するイメージ
※流れの向きは電池などの電源がつくる「+と-の差」によって決まり、電子はその差に押されて“マイナス極 → プラス極”へ流れます。
フォトンビームも光の照射だけで電気エネルギーを発生
照射が空気、水中に関係なく電気(電流)を発生させ、その電気がエネルギーを発生させていることが実験で明らかになっています。
これにより、
実験結果報告書
2.イオンとは?
通常の原子はプラスとマイナスの電気が釣り合って中性ですが、外からエネルギーが加わったり他の原子とぶつかったりすると電子が抜けたり増えたりします。
- 電子を失った原子・分子は、プラスの電気が多くなって「プラスイオン」になります。
- 電子を得た原子・分子は、マイナスの電気が多くなって「マイナスイオン」になります。
電子は分け与えることができる
電子をたくさん持て余している原子は、電子が不足している原子に電子を分け与えることができます。
ここでイメージしやすいように、原子を擬人化して擬人化した原子が持っている電子を他の人に分け与えることができるイメージ動画を用意しました。
電子は分け与えることができるイメージ
自分の電子が減り足りない状態がプラスイオン状態で不安定な状態。友達からたくさんもらい余っている状態はマイナスイオン状態で活性化している状態です。
3.電子のやり取りが生む「つながり」:化学反応
原子が安定するのは、一番外側の電子の数が「キリの良い数」になったときです。そのために、原子は余分な電子を他の原子にあげたり、足りない電子をもらったり、時にはお互いに電子を共有したりします。この電子のキャッチボールが化学反応そのものです。
例① 電子を渡してイオンになる:食塩(NaCl)
ナトリウム原子(Na)は電子が1個余っています。一方、塩素原子(Cl)は電子が1個足りません。ナトリウムは余っている電子を塩素にあげることでお互い安定します。
- 電子を失ったナトリウム → ナトリウムイオン (Na⁺)
- 電子を受け取った塩素 → 塩化物イオン (Cl⁻)
プラスとマイナスの電気は引き合うため、この2つのイオンがくっついて塩化ナトリウム(食塩)になります。
例② 電子を共有して分子になる:水(H₂O)
水素原子(H)は電子が1個、酸素原子(O)は電子が2個足りません。このとき、酸素は2つの水素と電子を1個ずつ共有します。まるで手をつないで安定を保つように「共有結合」が生じ、水分子が誕生します。
4.ミトコンドリアの働きと電子
私たちの体の細胞の中にあるミトコンドリアは、小さな「発電所」です。食べ物から取り出した電子がミトコンドリアの中をリレーのように次々と運ばれ、その過程で水素イオンが一方にためられます。たまった水素イオンが戻る力でATPというエネルギー物質が作られる仕組みです。
この働きは、ダムにためた水が流れ出して発電する様子に似ています。電子が燃料、水素イオンが水の重さ、ATP合成酵素が発電機と考えるとイメージしやすいでしょう。
5.電子の応用と歴史
比電荷と電子の発見
1897年、J.J.トムソンは陰極線実験で電子の存在を示し、その「比電荷(電子が持つ電気量を質量で割った値)」を測定しました。比電荷は電子の基本的な指紋のようなもので、この実験が電子物理学の始まりです。1913年にはR.A.ミリカンが油滴実験で電子1個の電気量を測定し、電気が離散的であることを確かめました。
半導体と省エネ技術
現代では電子の性質を利用した半導体が省エネ技術の要となっています。炭化ケイ素(SiC)製パワー半導体は、従来のシリコン製よりオン抵抗が小さく、電力変換時のエネルギー損失を約3分の1に抑えることができると報告されています。これは産業技術総合研究所(AIST)の研究に基づくもので、電気自動車の航続距離を伸ばし、社会全体の省エネに貢献すると期待されています。
MEMSセンサーとIoT
MEMS(メムス:Micro-Electro-Mechanical Systems)とは、微小な機械構造と電子回路を1つのチップに集めた技術です。MEMS圧力センサーは米粒ほどの大きさで、わずかな気圧の変化を検出し、消費電力は0.2mWと非常に低い。この技術により、スマートフォンやウェアラブル機器で高度や動きを精密に測ることができます。
6.まとめ
- 電子は負の電気を持つ小さな粒で、電流や化学反応の源
- イオンは電子を失ったり得たりした原子や分子で、電気を帯びている
- 化学反応は電子のやり取りや共有によって起こり、食塩や水など身近な物質が作られる
- ミトコンドリアは電子とイオンの流れを利用してエネルギー(ATP)を作る細胞内の発電所
- 電子の性質を生かした半導体やセンサー技術は、省エネやIoTに欠かせない
出典
最後に、検索エンジンからの流入を意識するなら、「中学生でもわかる電子とは?イオンの仕組みまでやさしく解説」といったタイトルにすると、ターゲット読者が探すキーワード(「電子 とは 中学生」「イオン 仕組み」など)を含められます。